灯し続けることば/大村はま … 胸に響く52のことば
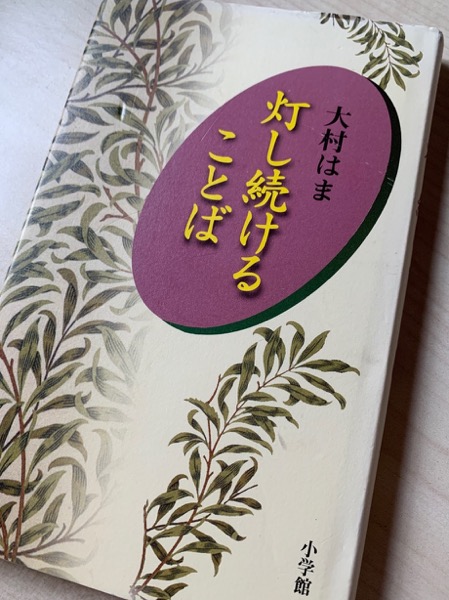
語り口調は柔らかいのですが、教師に限らず親や全ての人の胸に響くような「灯し続けることば」が詰まっています。明治39年生まれの大村はまさんですが、まったく古さが感じられない作品です。そして、52年の教師生活にちなんでだと思われる「52の珠玉のことば」が綴られています。
Contents
『 灯し続けることば 』の基本情報
まず、『灯し続けることば』は、2004年に小学館から発行されました。大村はまさんの52年の教師生活における「52の珠玉のことば」が綴られています。
著者の「 大村はまさん 」について
1906年 横浜生まれ。東京女子大学卒業後、長野県諏訪高等女学校で52年の国語教師ての生活を送ります。さらに、定年退職後は「大村はま 国語教室の会」を立ち上げ、子供たちに本当のことばの力をつけるための実践を続けられました。
大村はま文庫
1995年に「大村はま文庫」として、「文献」のほか「単元学習実践資料」「学習の記録」など、およそ9,000点が「鳴門教育大学附属図書館」に寄贈されました。また、鳴門教育大学のHPには『大村はま「学習の記録」の特質』として「学習の記録」について詳しく説明されています。
主な著書
『新編 教えるということ(ちくま学芸文庫)』筑摩書房
本当の『教える』ということを「教師の仕事」「教室に魅力を」「若いときにしておいてよかったと思うこと」などから、教師のあるべき姿や教育に取り組む姿勢について、エピソードを交えて語られています。
『新編 教室をいきいきと〈1〉(ちくま学芸文庫)』筑摩書房
『大村はま講演集〈上〉人と学力を育てるために』(上下)風濤社
『日本の教師に伝えたいこと(ちくま学芸文庫)』筑摩書房
『大村はま優劣のかなたに―遺された 60のことば(ちくま学芸文庫)』筑摩書房
『大村はま自叙伝 学びひたりて』 共文社
関連書籍
『時代を拓いた教師たち―戦後教育実践からのメッセージ』日本標準
戦後教育に多大な功績を残した教師たちの実践集です。なお、「大村はまと国語単元学習ー教えるということを問い続けてー」にて紹介されています。
『 灯し続けることば 』作品の概要
「52のことば」は、大村はまさんが教室を舞台に奮闘した中から生まれたものなので、教師と生徒のやり取りがもとになっています。教員はもちろん、親や部下を持つビジネスマンなど多くの人の胸にしみることばです。
また、教師というと「子供のために」と自分を犠牲にしながら愛情を注ぐイメージをもつ人もいるかも知れませんが、大村はまさんは違います。
「教室で子供がかわいいと思ったことはありません」と言い切っておられ、いかに次の手を打つかで頭がいっぱいということです。「子供のために」というより「子供の将来のために」ということなのかもしれません。
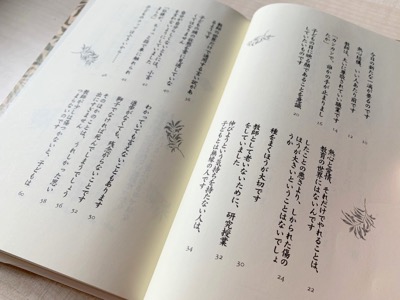
『 灯し続けることば 』の作品詳細
「52のことば」のうち、とくに親目線で注目すべき3つのことばを紹介します。
「ことばの教育を問いなおす──国語・英語の現在と未来」(ちくま新書)
「 子供の目に映る顔であること 」を意識していたいものです
子供が発表を終えると指導者の方をチラッと見るもの、そのときに 子供に顔を見られる準備をしておく というものです。そして、こんなとき、ねぎらいの気持ちを持って目を合わせたいと常々と考えておられたそうです。
もしかしたら、家族生活の中でスマホの画面を見たまま子供と会話してしまうこともあるかもしれません。しかし、しっかりと目を見てあげることによって子供に安心を与えることも大切ですね。
「 種をまくほうが大切です 」
子供を「褒めること」は大切なことです。しかし、いいことがあったら褒めるというのでは その場面が来るまで褒めることができませんし、簡単なことをやって褒められても いい気持ちはしません。そのため、 褒めるより「褒める種をまくこと」のほうを大切にしていたそうです。
褒めることも必要だとは思いながらも、なかなかうまくいかないことはあります。褒める場面をお膳立てするというよりは、「褒められるような行動を引き出してあげる」 ということで子供は成長していくのかもしれません。
「 最初に浮かんだことばは、捨てます 」
花を見て最初に浮かんだ「きれい!」という言葉は言わないでおいて、「何がきれいなのかという理由を考えてから言葉を発する」ようにされているということです。これが言葉を磨くコツの一つではないか とおっしゃっています。さらに、言葉を豊かにするということは、人間として素晴らしいことであり、生涯心がけていくべきことだと結ばれています。
「きれい!」という言葉は、実は、自分の好みであるかどうか、または、プラスイメージであるというざっくりしたものだけであることが多いのかもしれません。それが「どのようにきれい」であるのかを考えたときに、思考がなされたり、分類したり、人との会話では理解が深まったりするのですね。
関連リンク
最後に、関連する本の紹介です。
子育てと本
子育てと本や勉強との関係
・図鑑 … 「子育てにいい」というのは 本当か?
・本を読むと読解力がつく というのは 本当か?
・仮親 … 江戸時代からの仮親制度から学ぶ ポイントは?
・百ます計算 … メリットとデメリット、 上手く使うには?
子供向けの本
・ことばを増やす 本選び … 小学生や中学生の ことばを増やす
・山中伸弥さんが 子供の頃に読んだ本
・小学生のための論語 … 声に出して、わかって、おぼえる!
・じょうぶな頭と かしこい体になるために / 五味太郎
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1902e8fc.c6aaaf18.1902e8fd.b1377dbd/?me_id=1213310&item_id=11269698&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0984%2F09840090.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0984%2F09840090.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)




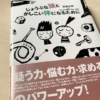



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません