2歳で包丁 … 心配しながらも包丁を使ったお手伝い

まだできない年齢のときは「やらせてー」と言い、できる年齢になって頼むと「えー」と言われるお手伝い。難しいものです。小さいうちからのお手伝いは成長につながるものと思いますが、「2歳で包丁」となると心配もあります。我が家での経験を書いてみました。
Contents
「2歳で包丁」などのお手伝いについて
料理のお手伝い
お手伝いにもいろいろあるのですが、うちでは料理のお手伝いは早めにやってきました。具体的には、包丁で切ったり、フライパンで炒めたり、お米を研いだりということなど。
もちろん、自分でやったほうが速くて確実なので、余計に手間がかかったり時間がかかったりするのは覚悟の上で「子育てと割り切って」やるようにしています。
「2歳で包丁」を使うこと
上の3人に包丁をもたせたのは2-3歳ぐらい、4人目も3歳なのでそろそろかなと思っているところです。包丁や火を使う(IH)のは少し心配でしたが、やってみればなんとかなるものです。
「集中力」
子供は、よく人の顔を見ますよね。親が包丁を使っているときに真剣な顔つきをしているので、子供は親の顔を見ながら「これはただ事ではないぞ」とわかるのでしょうか。ただ、子供なりに集中して真剣にやっているように見えます。手先が器用になるよりも、集中力を養う訓練としてのほうが効果があるのかもしれません。
「セラミック包丁」
もちろん、最初は親のほうで手を添えながらだったり安全には気を配りながらですが、それほど問題なく使えているようでした。
しばらくすると、料理をしていると話した親戚から「子供用のセラミックの包丁」をいただきました。しかし、見た目が「おもちゃ風」に見えるせいか指を切りかけたことがありました。大きさや重さは子供向き、油断がなければ「子供用セラミック」のほうがよさそうです。
「IH」でフライパン
親自身は火が出る「ガス」を使ってきましたから、「IH」しか知らずに育った子供たちの感覚はちょっとわかりません。それでも、油がはねたりして熱いことはわかりながら、なんとかやっています。休みの日の朝は、子供たちのうち誰かが「目玉焼き」をつくっている感じです。なお、次の写真は三男が「小1」のころだと思います。

学校では教えてくれない大切なこと19 楽しくお手伝い(旺文社)
「2歳で包丁」まとめ … 手先だけではない「成長」
「手伝い」とはいえ、あくまで「子育て」
「2歳で包丁」を持った結果、「ままごとより本物のほうが楽しいに決まっている」ということなのか、上の子を見ていると小学校低学年ぐらいまでは積極的でした。しかし、小学校低学年までは、それほど戦力にはなりませんので「手伝い」というより「子育て」ですね。とくに幼児ぐらいだと、こぼしたりちらかしたり時間が何倍もかかったりします。
「生の体験」から得られるもの
小さいうちの「生の体験」は貴重なものなので、「こぼす」「ちらかす」「時間がかかる」という前提で「子育て」だと思ってさせるようにしています。そんな中で、危険も伴うので集中しますし、切ると形状が変わったり、フライパンの中で食材のようすが変わっていくことを見たりすることで、さまざま成長があるはずです。そのため、うちの4番目にも、これからどんどんお手伝いをさせようと思っています。
関連リンク
最後に、関連する本の紹介です。
「子育て関連」
・図鑑 … 「子育てにいい」というのは本当か?
・考える力 をつける親子の会話とは?
・本を読むと 読解力がつくというのは本当か?
「子育てと本」
子供向けの本
・ことばを増やす 本選び … 小学生や中学生の ことばを増やす
・山中伸弥さんが 子供の頃に読んだ本
・じょうぶな頭と かしこい体になるために / 五味太郎
・小学生のための論語 … 声に出して、 わかって、 おぼえる !
・こども「学問のすすめ」 … だからぼくは勉強するんだ
保護者向けの本
・灯し続けることば / 大村はま … 胸に響く 52のことば




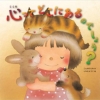



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません